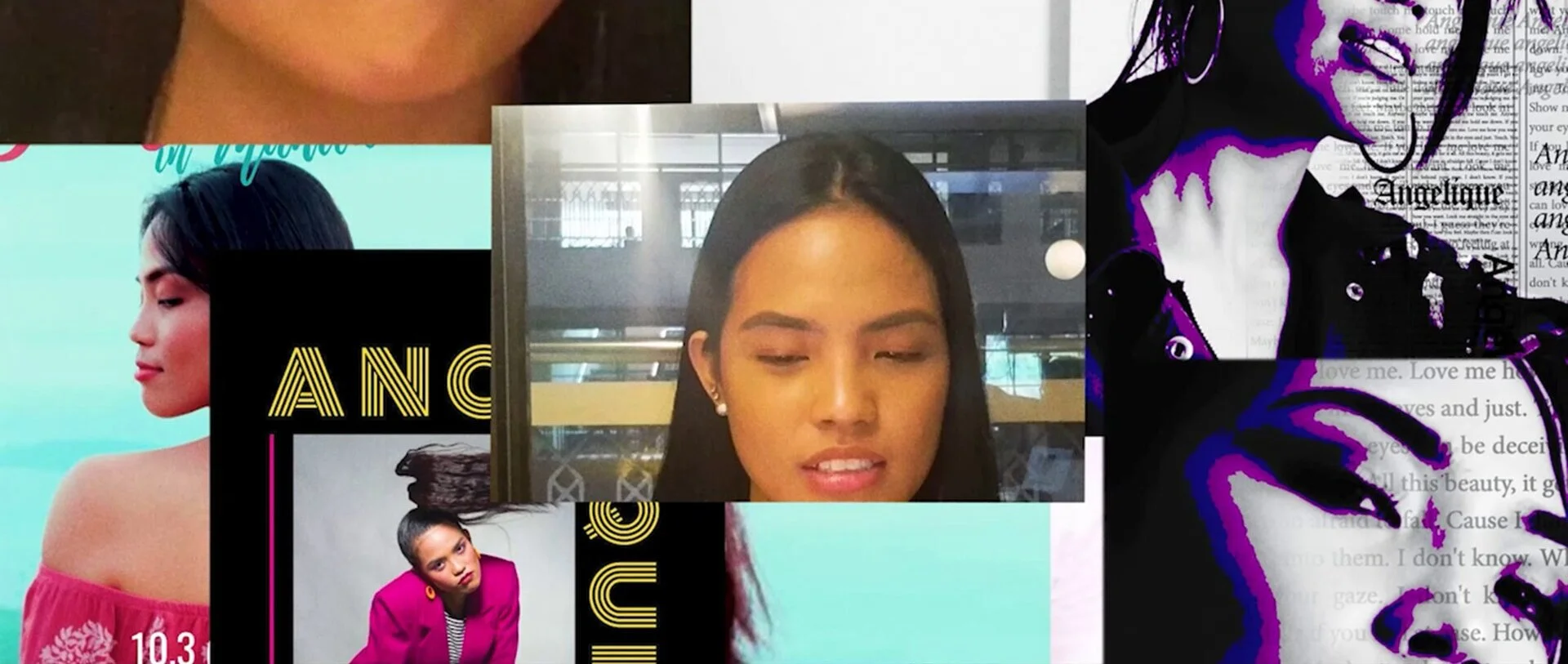スコールが通り過ぎるのを待つように。 東南アジアの性的少数者映画をめぐる近況
/特集[クィア東南アジアの今 その声のいくつか]のために、東南アジア圏の映画を研究/調査されている坂川直也さんに、東南アジアにおける近年のクィア映画の状況について寄稿いただきました!リンクをひらき予告映像などを見ながら、ぜひ読んでください。
スコールが通り過ぎるのを待つように。
東南アジアの性的少数者映画をめぐる近況
坂川直也 Naoya Sakagawa
2021年11月19日
2021年4月に出版された『東南アジアとLGBTの政治——性的少数者をめぐって何が争われているか。』(明石書店)に、第二章「現代東南アジアにおける性的少数者映像、その類型化の試み」という論文を寄稿した。その関連で、今回、ノーマルスクリーンの秋田祥さんから、「特集:クィア東南アジアの今 その声のいくつか」に関連して、東南アジアの性的少数者に関する映画の近況を書いてもらいたいという依頼を受け、論文以降、どういう動きがあったのかを書いてみたい。
「現代東南アジアにおける性的少数者に関する映像、その類型化の試み」で、性的少数者に関する映像をめぐる公共性について検討した。性的少数者に関する映像の公共性を検討する基準として、①アカデミックな研究、②性的少数者に関する映画祭、③国内映画祭での受賞歴の有無を用いた。そして、論文では以下のような暫定的な判断を書いた。
「東南アジアで性的少数者映像をめぐる公共性が最も高い国はタイとフィリピンで、ベトナムがそこに追いつこうとスピードを上げている。インドネシアはここ二、三年で後退し、そのインドネシアを、最近、BL(ボーイズラブ)ドラマを制作するようになったミャンマーが追い越そうとしている。」
今からすると、もっとも大きく変わったのはミャンマーの情勢である。2021年2月1日に起きたミャンマーのクーデターは、『東南アジアとLGBTの政治』の出版前ではあるが、論文の執筆後だった。現在のミャンマーでは、性的少数者に関する映像ももちろん、劇映画全般を制作するには困難な情況で、制作されるとすれば、ドキュメンタリーもしくはニュース映像に限定されるだろう。今回の特集で配信された『シンプル・ラブストーリー』(ミャンマー 2017年) は、日本での最初の上映は京都大学東南アジア地域研究研究所「Visual Documentary Project」(VDP)、2020年「愛」特集だった。私は近年、VDPの予備審査を担当していて、ミャンマーから『シンプル・ラブストーリー』以外にも、性的少数者に関するドキュメンタリーが多数応募され、やはり、ミャンマーとタイの隣国で、性的少数者に関する映像の創り手たちがたくさんいたんだなと感動した覚えがある。しかし、インドネシアを追い越そうとしていたミャンマーもクーデターによって、性的少数者に関する映像を制作できる環境から遠のいてしまった結果に、インドネシアの後退同様に、東南アジアの政治体制における不安定さが性的少数者に関する映像をめぐる公共性に影響を及ぼしていることを痛感した。
東南アジアで性的少数者に関する映像をめぐる公共性が最も高い国は依然、タイとフィリピンで、今回の特集で、この両国の作品が配信されている点でも裏付けされている。論文で「東南アジアにおける性的少数者映像の最新潮流である、BLドラマ」と述べたが、「タイ沼」という言葉が広がるほどに、タイ発のBLドラマは、日本でも動画配信サービスなどで人気を博している。さらに、「フィリピン発BLドラマシリーズ「GameBoys(ゲームボーイズ)」の続編にあたる映画『ゲームボーイズ THE MOVIE ~僕らの恋のかたち~』が、2022年1月21日に公開される。
ちなみに、この『ゲームボーイズ THE MOVIE ~僕らの恋のかたち~』は、 第8回台湾国際クィア映画祭(TIQFF)2021のクロージング作品にも選ばれている。『ゲームボーイズ THE MOVIE』のエグゼクティブ・プロデューサー、そして共同脚本家に、『ダイ・ビューティフル』(2016年)のジュン・ロブレス・ラナ監督が入っているのが興味深い。ラナ監督は『ダイ・ビューティフル』以降も、バクラをめぐるコメディ映画『The Panti Sisters』(2019年 ブラザーズではなく、シスターズというところがミソ)、アジア映画サイトAsian movie pulse選出「アジア発偉大なモノクロ映画25」の10位 、HIVに感染した15歳の少年が主人公の『Kalel, 15』(2019年)、クリスマス公開予定の最新作でコメディ『Big Night』(2021年)など 硬軟交えた性的少数者周辺の映画を監督しているので、日本未公開なのは惜しい気がする。
タイとフィリピンの性的少数者に関する映像をめぐる公共性の高さは、トランス女性監督の活躍からも伺える。タイからは、上映会『QUEER VISIONS 2018』で、秋田さんと私が解説したプログラム「映画監督ノンタワット・ナムベンジャポンが過去16年から選んだタイのクィア短編5 本、87分。」で上映された『ディープ・インサイド』のタンワーリン・スカピシット監督は、その後、タイ初のトランスジェンダー国会議員になった。 『エロティック・フラグメンツ 1、2、3』のアヌチャー・ブンヤワッタナ監督(長編『別れの花』)は、HBO Asia初のタイ語オリジナルシリーズのドラマ『Forbidden』を共同監督、GMMTVのBLドラマ『Not Me』 (2022)の監督をされる。フィリピンからは、イザベル・サンドバル監督がニューヨークを拠点に活躍されている。彼女の現時点での代表作と呼べる『LINGUA FRANCA』(2019年)を始め、彼女の長編作品は日本で上映される機会に恵まれていない。彼女のツィッターは示唆とウィットに富んでいるので、彼女の本格的な紹介が日本でなされることを願ってやまない。もっとも、タイとフィリピンにおいてさえ、論文で、「トランスジェンダーを取り上げた作品においても、トランス男性よりも、トランス女性を取り上げた作品のほうが圧倒的に多い」と書いた状況は、いまだに変わっていない。
同様に、今回の特集で配信された、タンサカ・パンシッティウォラクン監督『叫ぶヤギ』(2018年)のように、女性同士のカップルを取り上げた作品はタイにおいてもまだまだ少ない。余談だが、Asian Film Joint 2021のフォーラム「02. 2564年のタイとインディー映画」の配信を視聴していたら、ドンサロン・コーウィットワニッチャー(映画評論家/プロデューサー)さんのプレゼンで、政治について語ってきたタイのインディペンデント映画のうち、タイ国内で上映禁止もしくは困難だった作品4本を紹介されていて、うち2本が、『QUEER VISIONS 2018』でタイのクィア短編を選んだ、ノンタワット・ナムベンジャポン監督『空低く 大地高し』(2013年)と、『叫ぶヤギ』のタンサカ・パンシッティウォラクン監督の長編『Supernatural』(2013年)だった。秋田さんと京都でお会いした時に、タンサカ監督の作品、特に長編はタイ国内で公式に上映は難しいが、果たして、日本国内でも上映可能でしょうかという話をしたことをふっと思い出した。つまり、性的少数者に関する映像をめぐる公共性の高いタイにおいても例外はあり、政治的な作品、性器が映っている作品は上映が難しい。さらに、日本において、タイの性的少数者に関する映像作品上映と比較した場合、フィリピンは未上映作品が多い。もちろん、作品数自体が多いのもあるが、フィリピンのBLドラマの紹介とともに、フィリピンの性的少数者に関する映像作品の紹介も増加するのか、注目している。
タイとフィリピンに追いつこうとスピードを上げているベトナムだが、男性同性愛映画『こんなにも君が好きで -goodbye mother-』(2019年) まで日本で配信されて、驚いた。ベトナムでは、性的少数者の映像作品は増えている。たとえば、『こんなにも君が好きで』主演俳優ライン・タインが出演した映画『姉姉妹妹』(2019年)、『ソン・ランの響き』の主演リエン・ビン・ファットが出演、『Mr.レディMr.マダム』(1978年)と原作が同じ、ラブコメディ『Butterfly House』(2019年)、そして、今回の特集で配信されている『フウン姉さんの最後の旅路』(2014年) を劇映画化した『ロト』(Lô Tô 2017年)など、性的少数者の姿を「親しみのある隣人」として描こうとする娯楽映画も増えている。特に、『ロト』と『Butterfly House』を監督した、フイン・トゥアン・アイン(Huỳnh Tuấn Anh)は注目すべき監督かもしれない。インディペンデント映画のほうでも、『第三夫人と髪飾り』のアッシュ・メイフェア監督はトランスジェンダーの若者を主人公にした長編『SKIN OF YOUTH』を制作中で、ノーマルスクリーンで以前『赤いマニキュアの男』(2016年)が上映された、チューン・ミン・クイ監督(『樹上の家』他)は、初老のゲイを主人公とした短編『Les Attendants』(The Men Who Wait 2021年)を撮った。しかし、2021年はコロナ禍でベトナム映画の制作本数、上映本数が減少することが予想されるので、性的少数者の映像作品にもどのような遅延や停滞をもたらすのか、先行きは不透明である。
インドネシアでは、すっかり性的少数者に関する映画が制作されなくなってしまった。2002から2017年まで続いた「Q! フィルムフェスティバル」の休止が象徴的だった。Q! フィルムフェスティバル休止に関する、創設者John Badaluの声明文に、インドネシアにおける性的少数者に関する映画祭関係者、そして映画人たちが置かれた苦境が伺える。 ちなみにJohn Badaluは、先に述べた、タイのアヌチャー・ブンヤワッタナ監督による長編『別れの花』(2017年)、ベトナムのチューン・ミン・クイ監督による短編『Les Attendants』(2021年)のプロデューサーでもある。ただし、インドネシアにおける性的少数者映画をめぐる苦境は現在も変わらず、今にして思えば、ガリン・ヌグロホ監督『メモリーズ・オブ・マイ・ボディ』(2018年)が最後の輝きだったかもしれない。論文で取り上げた、ルッキー・クスワンディ監督にしても、ゲイに関するシットコム『CONQ』(2014年)、短編『虎の威を借る狐』(2015年) あたりがピークで、性的少数者というテーマからは退っていった。また、インドネシア映画史上初めてゲイというテーマに正面から取り組んだ『アリサン』 (2003年)で、知られる女性監督ニア・ディナタの最新作『恋に落ちない世界』(2021)もネットフリックスで10月から配信が始まった。脚本はルッキー・クスワンディ監督との共同で、近未来のディストピアSF映画である。ニア・ディナタとルッキー・クスワンディの共同脚本と言えば、ルッキー監督が女性同性愛者のカップルを主軸に据えた群像劇『太陽を失って』(2014年)の頃ではあれば、次は性的少数者のテーマにどう取り組むのか、わくわくしただろう。『恋に落ちない世界』は17歳前後の未婚である少女3人組を主人公にした、女性の自立を観客に問いかける女性映画である。そして、『メモリーズ・オブ・マイ・ボディ』と制作会社Fourcolors Filmsも、プロデューサー(イファ・イスファンシャ監督)も同じで、第22回フィルメックスで上映された、ガリン・ヌグロホの娘であるカミラ・アンディニ監督の最新作『ユニ』(2021年)も、高校の最終学年に通う、未婚の少女を通して、女性の自立を観客に問いかける女性映画だった。ちなみに、『ユニ』に出演している女優アスマラ・アビゲイル(1992年~)は、『恋に落ちない世界』にも出演していて、彼女はガリン・ヌグロホ監督『サタンジャワ』(2016年)主演女優でもある。
さらに、2017年の東京国際映画CROSSCUT ASIA提携企画「カラフル! インドネシア2」の『インドネシア短編映画傑作選』で上映された短編『申年』(2016年)の新鋭監督レガス・バヌテジャ監督(1992年~)による、長編デビュー作『PENYALIN CAHAYA (Photocopier) 』は、パーティに参加し、意識を失った大学生の女性が、自撮りした写真をネットで拡散され、幼なじみと自撮り写真流出とパーティの夜の真相を明らかにするミステリーで、2022年1月13日にネットフリックスで配信予定である。このように、インドネシアの先鋭的な監督たちがこぞって最新作で、10代後半の少女たちを主人公に据えている点で共通していて、注目に値する。つまり、インドネシアでは、性的少数者に関する映画が制作されなくなってしまったが、代わりに10代後半の少女たちという主題が台頭してきた。彼女たちが直面する苦闘や葛藤を映し出すことで、社会的弱者への暴力、理不尽を浮かび上がらせ、観客に問いかける作品は健在であると言えるだろう。時代の潮流と制約の中で、性的少数者という題材が10代後半の少女たちへと変化したのだ。これらの少女たちの映画が、将来の性的少数者に関する映画のさらなる飛躍につながるのか、単なる退潮や衰退に終わるのか、現時点では正直、予想がつかない。しかし、個人的には、インドネシア、そして、ミャンマーにおいて、性的少数者の映像作品が復活する日を待ち望んでいる。スコールが通り過ぎるのを待つように。